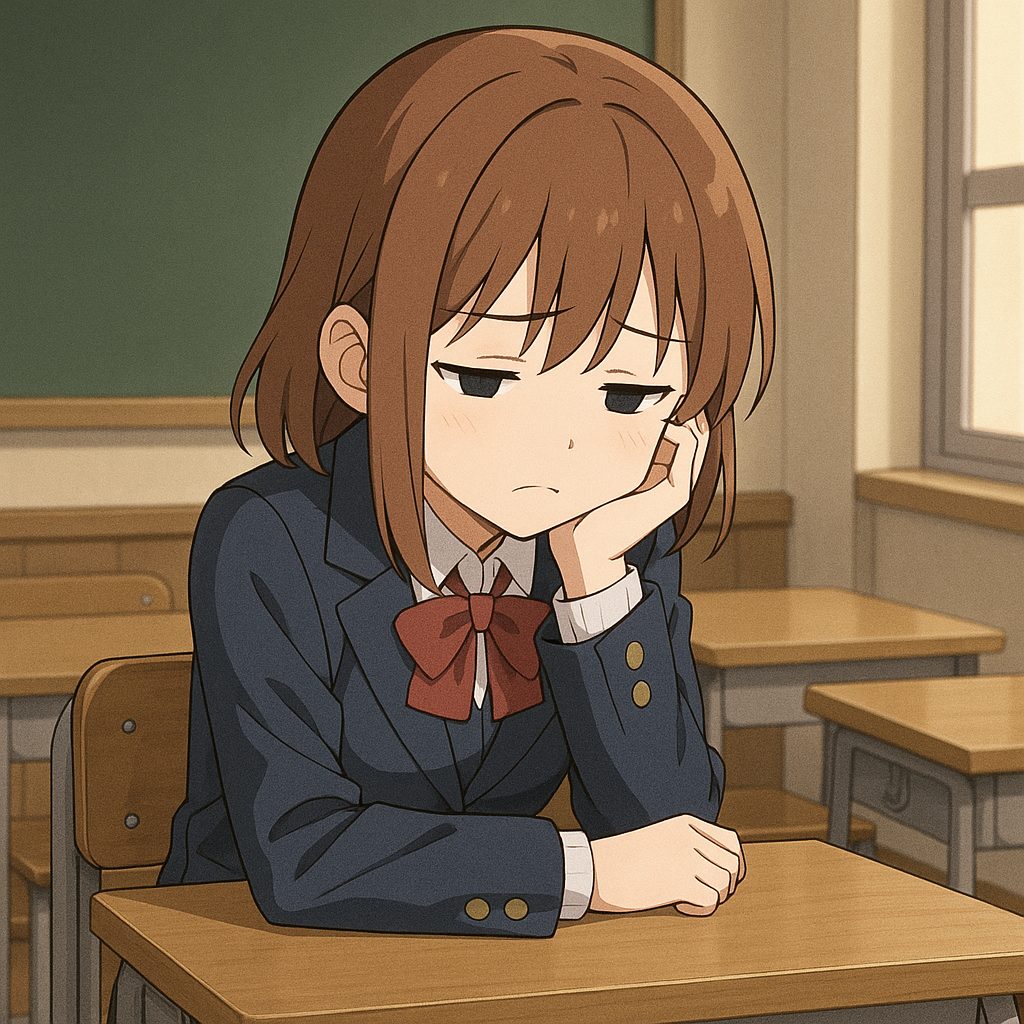
足りなかったのは、「第1志望大学学部に合格するため」の実績作りの時間、自分のテーマを深堀りする時間、小論文を鍛える時間など。
一般入試対策は、当然ながら、お子様が小さいうちから準備を重ねていきます。例えば、小学校受験や中学校受験、あるいは、高校受験、環境の良いインターや留学を視野に入れているご家庭は、お子様を少しでも上の大学、またその先の就職をみているからだと思います。むろん、それだけではない、校風や学びや環境などの要素も多数あると思いますが、本質のところは学歴の比重が高いのではと感じます。
総合型選抜・推薦入試も同じ大学入試でございます。一般入試も総合型選抜・推薦入試も戦略と戦術が必要です。やみくもに勉強しても、「時間の非効率化」とともに「合格率」が下がります。総合政策選抜・推薦入試は1次試験と2次試験がありまして、難関校ほど1次試験のいわゆる志望理由書などの書類試験などの1次審査の足切りが多いです。つまり、ここを突破しないと2週間後や1ヶ月後の2次試験の小論文と面接試験に挑めません。もちろん足切りがない大学もございます。
1次試験の出願が一般的に、8月から9月なので、例えば、高校3年生の4月から準備を始めるとします。これを一般入試に置き換えると、高校3年生の冬近くになってから大学受験対策をはじめるということになります。上記事項を繰り返しますが、総合型選抜・推薦入試も一般入試と同じ大学受験です。ここをしっかりと抑えておくとお子様の為になるのではないかと、毎年深く思う次第でございます。どの入試でも「先手必勝」、あるいは「先んずれば人を制す」は古今東西、時代が流れても変わることのない普遍の法則でしょう。

しかしながら、生徒さんによっては、上記の時期からの準備で合格することもございます。それはお子様の適正と今までの活動などが志望校学部の求める人材と重なって起きる結果だと思います。当然ながら、お子様の士気も高いです。加えて、自分で考え、意思決定ができ、能動的に動ける、あるいは研究に没頭できる生徒さんが多い傾向にあります。能動的な性格で、且つ、調べ学習に慣れている生徒さんともいえるかもしれません。だが、これは慣れであり、新たなマインドを加えていけば、講師側のコーチング力にもよりますが成長してくものでございます。
入試は一般的に情報戦です、特に総合型選抜・推薦入試はそうでしょう。しかし、生徒さんが通われている学校によっては、総合型選抜受験の情報が少ない、あるいは、あやふやである高校が大多数でしょう。加えて、出回る情報というのはあなたとは違う人の情報であります。つまり、あなたとは違う適正の方の前提条件です。このことを鑑み、お早めに無料体験授業で生徒さんが、この試験について考え、試してみることをお勧めします。大切なのは己の思考の中で意思決定を繰り返すこと、2次情報より、圧倒的に大切な1次情報です。
理由の一つとして、たしかに、合格への戦略と戦術、テクニックと情報があります。しかしながら、総合型選抜・推薦入試は、従来の教育と異なる、答えがない、解がない試験です。例えば、このAI時代に暗記重視の偏差値至上マインドは、大学、社会人となりアウトプットがもとめれらるようになる中でどこまで必要なのでしょうか。むろん、背景となる知識は当然ながら知っておいたほうがいいですし、双方の良さがあり、また議論もあるでしょう。私自身、暗記の仕方にも試行錯誤が必要であり、隙間時間の取り方、体型的な考え方を必要とすることや、大学入試からも文理問わず思考力を必要とする出題など素晴らしいものがあると思います。
ともあれ、この試験は、多数の方が考えているような甘い試験ではないと思います。一度、環境(其々の方のポジショントーク)と価値観のバイアスを取り除き、考えてもらえればと思います。
横浜未来義塾講師一同、皆様をお待ちしております。
塾長
